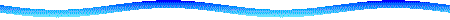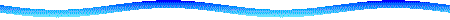
手がかかる子を排除していいのか?
――診断マニュアル口実に変質していく公教育
埼玉県教育局は、LD(学習障害)やADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもが教科によって通常学級・特殊学級・養護学校で学ぶかどうかを「選択」する制度を始める方針で、今年度中にも熊谷・坂戸市のモデル校で実施することを検討中という。(読売9・29夕)
「専門家」がLDやADHDの診断を下す時めやすとするものは、DSM-IV(精神疾患の診断と統計マニュアル・第4版)というアメリカ精神医学会が作成したものの直輸入版である。
このマニュアルはほとんどすべての精神疾患の診断の基準となる症状が記載されている。羅列された症状の中で何項目以上該当していれば○○障害であるとしているので誰にでも一見わかりやすい。カタログのようなもの。県教育局が夏休み中に全中・小学校で秘かに実施した調査の項目もDSMにのっとっている。(小さな新聞8月号掲載)
家庭・学校・社会の事情や背景、またそれらを含む沢山の要因を織り込んだ「個性」をぬきにしたとりあえずの分類であるものが、医師や臨床心理士が間に入ることで、障害や病気についての最新かつ普遍的な真理であるかのように確立していく。
しかし、ADHDなどの「障害」そのものが一体あるのかという専門家も多数いる。LD、ADHDの症状が顕著に現れ問題とされるのは学校であり、子どもの特性といえるものがDSMの項目の中には多く含まれている。DSMはますます細分化されている。細分化することによって投薬や配慮が便利になるからである。その場合、わけないために使うのか、わけるために使うのかがポイントである。社会でいっしょにやっていくための「おりあい」をつけていくことが前提なのか、まわりの迷惑を解消するためなのか。子どもの生活の場である学校をわける「支援」は本末転倒だろう。