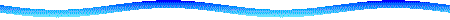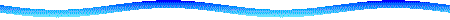
重度障害者にとって医療とは
――身近な医療機関もやはり大切――
両親が亡くなり武里団地で24時間介助者の手を借りながら一人暮らしをしている田口由利子さんが尻もちをついて、大腿骨頸部を骨折した。金曜日の夜から手術をしてくれる病院さがしが始まった。土日を挟んでいたこともあり、なかなか引き受けてくれる病院が見つからなかった。
最初に受診した診療所では上尾リハに紹介状を書いてくれたが、上尾リハはこんな時には全く役に立たない。彼女が知的障害があり、てんかんの薬を服用していたことが難しかった要因である。全身麻酔で手術をする場合はてんかんの薬のコントロールが必要で、精神科もある病院が望ましい。後見人の大輔さんと介助者が電話をかけまくり、S病院を受診した。痛みと初めての経験で、大声をあげて吠えまくる由利子さんを前にして、整形外科の医者は、「うちは精神科はないけれど、やる気があるかどうかだから」と手術の予定を決めた。由利子さんは無事手術を受けて退院した。
「障害者専門の病院」がほしいという親の会の要望は根強くある。今回のような経験をすると、なるほど親だけで病院を探すのは大変だろうなとは思う。でも、「障害者専門の病院」てなんなんだろう。障害者もいろんな病気をする。全科そろった24時間対応のしかも医療的にも十分対応できる病院なんていうのは現実的ではないし、それがあれば事足りるのだろうか。障害者専門の病院がもしあったら、「ここはあなたたちの来る病院ではない」とますます地域の病院にかかりにくくなるだろう。それに、昔、某病院であったように障害者ばっかりを集めて人体実験のような医療がされる恐れはないだろうか。
普通の患者として普段から地域の病院にかかり、ネットワークを広げていくことが大切だろう。「要はやる気があるかどうかだから」という医者もいるのだから。