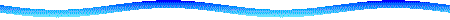小さな新聞2013年11月号(月刊わらじ連載)
医学・医療の倫理性とは?
治療なき発見・予防は抹殺への道
医療の場の臨床研究というからには、早期発見・早期治療という文脈の中での話だろうが、胎児の病気が早期発見できても治療ができるのは心臓の形成不全や胎児腫瘍に対する手術などごく一部でほとんどの場合治療できない。この場合、治療・予防とは中絶を意味する。胎児の先天異常を理由にした中絶は日本では認められていない。なぜ中絶できるのか。それは母体保護法の「身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れ」を拡大解釈しているからだ。新型出生前診断の対象となる三種類の染色体異常も治療の方法はない。
闇のなかで行われているので日本では「先天異常と出生前診断で判明した人の何割が中絶をしているか」のデータは公表されていない。が、横浜市大国際先天異常モニタリングセンターが国内330の施設を対象に調べた結果がある。それによると、出生前診断で胎児の異常がわかったことを理由にした中絶は、2000〜2009年の10年間で11706件と推定され、前の10年間に比べ倍増した。ダウン症に限ってみれば、1990〜99年は368件だったのが、2000〜09年は1122件と急増していた(読売2011.7.22――香山リカ・新型出生前診断と「命の選択」)出生前診断で異常とされた胎児の総数がわからないので、中絶をした人の割合はわからない。
米国では検査会社は年間売上585億円の巨大市場となっている。早期発見・早期治療ということで医療の場で障害胎児の早期抹殺が進められようとしている。