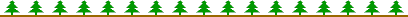|
就学判定廃止から出直そうよ! 8月29日 特振協 全体協議会で武井委員 |
|---|

|
就学判定廃止から出直そうよ! 8月29日 特振協 全体協議会で武井委員 |
|---|

県教委は、上記の中間まとめ案をかなり修正した中間まとめ最終案を、29日の特振協に提出します。この最終案では、上記「支援籍」制度を核にして、乳幼児検診とも連携して早期からの就学指導計画を立てようという、乳幼児期からのふりわけシステムの固定化がもくろまれています。出発点であった彩の国障害者プラン21の基本理念「分け隔てられることなく」や前知事の「全障害児普通学級籍」宣言から限りなく遠くに運ばれてゆこうとしているのです。
県教委や学識経験者とされる人々は、LDやADHD、高機能自閉症と呼ばれる子ども達を特殊学級等に通級させたり、特殊学級の子どもを盲・ろう・養護学校に通級させたり、盲・ろう・養護学校の子どもを入学式や卒業式といった行事に地元校に参加させるキセル方式などの案をもって、これこそ「障害のある子もない子も共に育ち、共に学ぶ」ことであると自画自賛しています。「みんなちがってみんないい」という詩を、きめ細かな選別のことばとして転用されるとは、故・金子みすずの無念はいかばかりでしょうか。
この29日の特振協で、ただ一人の幼いころからの障害者委員である武井さんから、①「支援籍」というわけのわからない方式を撤回し、すべての子どもが本来は地域の通常学級へ受け止められるべきであることを確認 ②就学指導委員会は施行令22条の3に基づく判定をやめ、共に学ぶことを相談・支援する機関に ③通常学級に在籍する障害のある子ども達の実態把握とそれに基づく支援 ④地域で受け止めきれない限界ゆえに特殊学級や盲・ろう・養護学校へ行かざるを得なかった子ども達の居住地交流の支援 などが提案されました(詳細は、後日)。
なお、以下に、中間まとめ最終案で新たに盛り込まれた箇所を中心に、深まる疑問点を列挙しておきます。
| 8.28向け特振協・中間まとめ案への疑問 |
|---|
1.「通常学級の障害児」数が初公表されたが
「市町村の就学指導委員会で盲・ろう・養護学校又は特殊学級への就学が望ましいと判断された児童生徒」のうち現在「小中学校の通常の学級に在籍する」児童生徒は、「平成15年5月1日現在、小学校に930人、中学校に181人」と、初めて公表された(3ページ)。しかし、このことが何を意味するのか、いっさい触れられていないのは、不思議きわまりない。共に育ち、共に学ぶことに対し、基本的にはなんら支援をしてこなかったばかりか、「ここは本来あなたの来るべきところではない」という扱いをしてきた中での〈1111人〉の重さを考えるべきだ。また、このほかに就学指導の対象にされながら、「通常学級適」とされた子どもが多数いるが、この子たちの存在はどう位置付けているのか不明。2.曖昧なまま強引に入れられたLD、ADHD、高機能自閉症
LDやADHD、高機能自閉症「により特別な教育的ニーズのある児童生徒の実態については正確な把握はできていないのが現状である。」(3ページ)と言いながら、その対応を「特殊学級を『支援籍(仮称)』として実施する」(20ページ)などという提案になりふりかまわず結び付けている。調査研究協力者会議の報告を「約6%の割合で通常の学級に在籍している可能性を示しているということである」(3ページ)と説明しているが、その「調査結果」レポートには「留意事項」として「本調査の結果は、LD・ADHD・高機能自閉症の割合を示すものではないことに注意する必要がある。」と記されている。3.認定就学者(全県で1名)問題には頬かむり
「学校教育教育法施行令の一部改正」については、それによって「『就学基準』の見直しがなされた」と述べられているのみ。そのポイントである「認定就学者」制度について何もふれられていない。本県の「認定就学者」が1人だけしかいなかったことをかくしている。本県では共に育ち・共に学ぶことを求める親子の強いはたらきかけを受けて、24年前の養護学校義務化の当時から「就学先決定に際しては本人・保護者の意志を尊重する」という確認が、県教委および多くの市町村教委でずっとなされてきた。「認定就学者」の場合は、「盲・ろう・養護学校適」という判定を妥当とした上で、例外として施設設備が整っていたり専門性をもった教員がいるといった「特別な事情」がある場合にのみ地元小・中学校にも就学できるという内容なので、本県の実態には合わない。だから「認定就学者」は1人しかいなかった。4.「全障害児に普通学級籍」はどこへ消えた
「障害のある全ての児童生徒が可能な限り地域の学校の通常の学級で」という文章がなくなり、「障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が子どもの頃から共に育ち共に学ぶ機会が徐々に拡大され」(4ページ)という表現になった。初めの文章では「可能な限り」というあいまいさはありながらも、「通常の学級」を基本とすることが明らかにされているが、後の文章ではその基本が消えてしまっている。「ノーマライゼーションの理念を実現させる『障害のあるなしにかかわらず』とは、広くこのような特別な教育的支援を必要とする児童生徒も含めて考えなければならない。」(6ページ)という部分などとあわせてみると、「LDやADHD、高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒」(6ページ)が特殊学級を通級的に利用するといった例が、後の文章の中にある「共に育ち共に学ぶ機会」であるらしい。(「実態については正確な把握はできてない」というのに、何が支援だ。)5.何も見直さない「就学指導の見直し」
「(2)就学指導の見直し」と銘打って、「障害の種類や程度の判断や就学の場の設定を検討するこれまでの就学指導を、本人や保護者への教育的支援や相談機能を重視する就学支援の観点や、学校や学級の枠を超えて児童生徒を支援する学習活動の実施の観点から見直すことが必要」(8ページ)と、まわりくどい説明をしている。抜本的に見直すのかと錯覚してしまう。また、次のように述べている。「これまで障害のある児童生徒の就学手続きは、その障害の種類や程度に応じた適切な教育の場を設定する観点から、盲・ろう・養護学校や特殊学級など学校(学級)の枠に児童生徒をあてはめた上で行われ」(13ページ)と。これを見直すべきと考えているのかといえば、さにあらず。その後にすぐ「教育効果を上げてきた」と肯定しているのだ。そして、「今後は、こうした現行の就学制度の基本は維持しつつも」とした上で、その基本を維持しながら障害の種類や程度により分けられた「適切な教育の場」の間の通級もありですと述べているにすぎない。しかし、「障害の種類や程度の判断や就学の場の設定を検討するこれまでの就学指導」こそが、子ども達を分け隔て、職場、地域を分け隔ててきた。「現行の就学制度の基本」となっている就学判定をやめることから始めるべきなのだ。6.危ういぞ!「乳幼児検診との連携」
「ア 就学指導実施計画の見直し」は危うい。「就学前のこどもたちの実態を十分に把握するために市町村が実施する乳幼児検診との連携も含め、継続的な実施計画の在り方が必要となる。」(8ページ)としている。「障害の種類や程度に応じて社会的自立につながる教育」(5ページ)を受けるためには盲・ろう・養護学校や特殊学級に行く必要がある(軽度の場合は支援籍=通級もありうるが)という就学指導を堅持しながら、「乳幼児検診との連携」などなされたらたまらない。7.「本人・保護者の意志尊重」確認はどこへ
これまでの「就学先の決定にあたっては本人・保護者の意志を尊重する」という確認をどう考えているのかはっきりさせるべきだ。「ウ 個別の教育支援計画を作成するための情報の整理」は、「就学先の決定や学校や学級の枠を超えて児童生徒を支援する学習活動は、個別の教育支援計画に基づき行われる。」「子どもの教育的ニーズに応じた就学先等の決定は、継続的な相談の過程で、教育学や医学、心理学等の専門家から助言を基に、保護者の意向も踏まえながら行うことが必要である。」(9ページ)とされている。これまでも「相談」とは名ばかりで「障害の種類や程度に応じた適切な教育の場」を強く勧めてきたのが就学相談の実態だが、たとえば「支援籍で通常学級の行事にも参加できるから養護学校に行きなさい、お子さんの将来のためです。」といった形で、いっそう執拗に行われかねない。8.介助員配置に努力の市町村に冷ややか
「(3)教育環境の整備」の中で、「介助員配置の現状は、平成15年5月1日現在、通常の学級への配置数が209人」(9ページ)とあるが、これは県教委として初めての実態把握である。「特殊学級への配置数が678人」とあるが、「特殊学級への配置数」についてはこれまでも交渉等で回答されてきた。しかし、通常学級への配置についてだけは、「市町村が独自の判断で行っているもの」として、地方分権を口実に、これまで県として実態把握を怠ってきたという経過がある。ただ、数を把握はしたが、「多くの市町村の場合、緊急雇用対策基金を導入して一時的に行っている現状」(9ページ)と冷ややかである。自転車操業的な形であれ、共に育ち・共に学ぶための支援を市町村が必死で先行させざるを得なかったのは、分ける教育だけを認知してきた県の基本姿勢に由来しているにもかかわらず、何の反省も語られていない。このように市町村が現に取組んでいる実態を県がきちんと認知することから、支援は始められるべきだ。ところが、県はそう考えないようだ。障害の種類や程度にかかわらず通常学級で共に学び続けられるための支援ではなく、あくまでも「学校や学級の枠を超えて児童生徒を支援するしくみを具体化する」(9ページ)、すなわち障害の種類や程度に応じた学校・学級に行きながら他の学校・学級も通級的に活用するといった形で、よりきめ細かに分け隔ててゆくためには、「施設・設備の充実はもちろん、人的支援は必要であり、県独自の教職員配置計画が検討課題である。」(9ページ)という。分け隔てれば隔てるほど、そこから地域で一緒に生きるためには二重三重の壁ができ、それらをこえるための大変な支援が必要になる。脱施設しかり、社会的入院解消しかりだ。しかし県教委はそれらから何も学ぼうとしていない。だから「その際、ボランティア団体などの社会資源の確保や導入に向けてのしくみづくりも併せて検討」などと、お気楽な言葉も吐けるのだ。9.社会にとって有害無益な「個別の教育支援計画」
「市町村は、障害のある子供たち一人一人のニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後までを目的としたこの個別の教育支援計画を作成しなければならない。」(15ページ)とされているが、「市町村は」と「個別の教育支援計画」の間がつながらない。「市町村は」と地方分権を語るのなら、まず国の学校教育法施行令22条の3別表に基づき「この子は障害の種類・程度がこれこれだから養護学校で教育を受けることが適切だ」といった判定作業を一切やめるべきだ。そのことによって、自動的に、障害のあるなしにかかわらずすべての子供は地域の通常学級で学ぶことが原則となる。例外的に本人・保護者の希望により、特殊学級や盲・ろう・養護学校で学ぶこともできるが、その場合でも市町村はその子たちが居住地の通常学級で受け止められるよう、継続的な教育・学習環境整備に努め、それを県は支援すべきなのだ。
「乳幼児期の個別の教育支援計画」が重要だとされ、「障害の状態等、実態を整理し、就学に向けての必要な教育的支援の方向性を整理」(16ページ)するのだという。彩の国障害者プラン21の第4章「自立に必要な力を高め、共に育ち、共に学ぶ教育を充実します」の「現状と課題」には、「幼稚園や保育所における障害児の受け入れについては、共に育ち、共に学ぶ場として重要であり引き続きニーズに応え推進する必要があります。」と述べられている。「乳幼児期」は「就学」のためにあるわけではなく、ましてや「障害の状態等、実態」を判定し分け隔てる教育を準備する期間として位置付けられるものではない。
「卒業後の個別の教育支援計画」として、「卒業後の就労等に向けて、これまでの学習の成果等を踏まえて必要な情報を整理」(16ページ)するという。「社会参加や自立する力を育む」(7ページ)ために「発達段階に応じた指導の充実や高等部における職業教育の実施が重要」(7ページ)などと述べられているが、本人が力を付け障害を軽減・克服するという発想では、軽度の障害者の一部が就職や一人暮らしにつながるだけで、多くの障害者が出口なき福祉施設に滞留してきたという現実から目をそらしてはならない。緊急に問われているのは、学校・職場を含む地域をこれ以上分けないことだし、分け隔てられた場から地域に参加してゆくことをどう支援するかだ。「個別の教育支援計画」としてくくられる内容は、こうした社会状況と相容れない。10.「就学支援委」・「作成委」なんていらない
「既存の就学指導委員会の活動を超えた委員会は、呼称も『就学支援委員会』とし、市町村及び県教育委員会は、人材の確保や学校との連携方策を整備する必要がある。」(15ページ)とある。「障害の種類や程度に応じて教育学、医学、心理学等の観点からの適切な指導」(15ページ)はいままでどおり行うとされ、今後はさらに分けられた教育の場の間の「通級」を加え、子供たちの生活をより細かく分け隔てる作業が加わるというわけだ。この「就学支援委員会」の専門的助言を継続的に受けながら、市町村が「児童生徒の個別の教育支援計画」を作成するとされている。ただし、「はじめて作成される乳幼児期」の「個別の教育支援計画」については、「乳幼児検診の結果等を踏まえ必要に応じて就学支援委員会が」、その「下部組織として」、「教育学、医学、心理学等の専門家に加え、対象の子どもに携わっている教育、医療、福祉機関の関係者で構成する」「作成委員会(仮称)」(いずれも16ページ)を招集し、作成に取りかかるとされている。6や9で述べたように、乳幼児検診の結果が就学指導に流用されるといった形での早期からの地域分離システムを許してはならない。11.よみがえろうとする「適格者主義」
「(1)障害のある生徒に対する高等学校における支援」として「後期中等教育における障害のある生徒に対する支援は、障害の種類や程度の外に学力や卒業後の進路などを踏まえ可能な限り多様である必要がある。」(23ページ)とされている。障害の種別や程度で分け、さらに学力や進路で分けるというのは、現状の固定化に他ならない。これまで県立高校入試において、「身体に障害があることにより不利益があってはならない」という当初の文言を「障害があることにより」と改定したり、国民的教育機関となった高校に知的な障害のある生徒も含め可能な限り受け止めてゆくために「定員内不合格はあってはならない」と確認してきたことを否定するものであり、とうてい認められない。12.高校の「介助員」をめぐって
「今後は厳しい財政状況なども踏まえつつ介助員配置や手話通訳、要約筆記など生徒の状況に応じた支援についても研究し、一層バリアフリー化を推進する必要がある。」(23ページ)とされている。現在、中学、高校などへの入試に関わる通知の中で「介助を行う職員の配置はできない」という「欠格条項」ともいうべき文言を削除できないと言ってきた県教委としては、一歩踏み込んだように思う。ただし、小・中学校の通常学級の介助員の配置については数を把握したのに対し、高校レベルでは数としてあがっていないのは問題だ。また、「バリアフリー化」と表現していることから、身体障害の介助に限定しているようにも受け取れる。いずれにせよ、まずは通知の文言削除からだ。